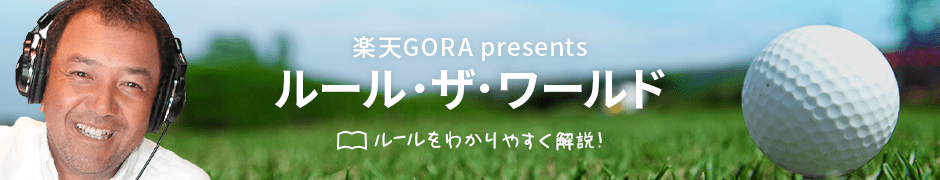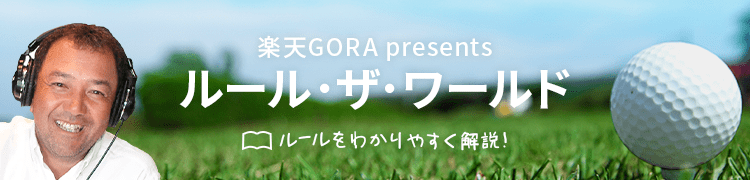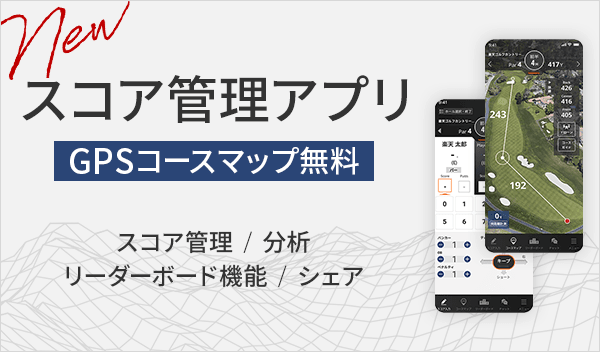- 5月3日(土)
- 笠りつ子選手のRPAの処置について解説:(JLPGA競技委員)阿蘇紀子さん、中崎典子さん
VポイントxSMBCレディスの2ndラウンド、13番ホールで起きたルーリングが大きなニュースになりました。
13番ホールは大会を通して難易度の高い390ヤードのパー4で、
ホールの左側はグリーンの奥まで続くレッドペナルティーエリアでした。
笠選手のティーショットはそのレッドペナルティーエリアに入り、ラテラル救済の処置を自ら行いました。
2クラブレングスの救済エリアの芝地はペナルティーエリアの方に傾斜していたため、
ドロップした球はペナルティーエリアを定める線の近くまで転がりましたが、
救済エリア内に止まったため、正しくインプレーになりました。
ところが、彼女は意図するスタンス区域がペナルティーエリアにかかったため、
再ドロップが必要と勘違いし、その球を拾い上げてしまいました。
2回目のドロップ後も同様に球を拾い上げ、2回目にドロップしたときにその球が最初に地面に触れた箇所に球をプレースしました。
そこからアドレスをしたところ、意図するスタンス区域がまたペナルティーエリアにかかったため、競技委員を要請しました。
立ち会った競技委員は選手から
「ラテラル救済の処置のためドロップを2回して球が止まらなかったので、2回目に球をドロップしたところにプレースしたのですが、
スタンスがレッドペナルティーエリアにかかります。これは大丈夫なのでしょうか?」
と質問されたため、
「意図するスタンス区域がペナルティーエリアにかかっていても球が救済エリア内にあればインプレーです」
と答えてルーリングは終了しました。
そして、彼女は誤った箇所にプレースした球をプレーしたことで、後に誤所からのプレーの一般の罰が課されました。(規則14.7a)
もし、競技委員が要請された現場でその誤りに気づくことができたら、ストロークを行う前でしたので、
1回目のドロップで球が止まった箇所にリプレースしてその誤りを訂正することができました。(規則14.5)
そうすることで、誤所からのプレーの一般の罰は免れることができますが、
例えその処置をしたとしても、インプレーの球を動かした規則9.4の違反による1罰打を免れることはできません。
そのため、レッドペナルティーエリアの1罰打を含む合計2罰打の4打目としてプレーすることができました。
しかし、実際は、3rdラウンドで最終組が終盤のホールに入った頃、委員会は大会関係者より前日の笠選手の誤った処置を知りました。
彼女に確認したところ、球をドロップした後はペナルティーエリアにスタンスがかかってはいけないと思い込んでおり、
その誤りに気づきました。
彼女は1回目のドロップで正しくインプレーになった球を拾い上げ、
その球が止まった箇所にリプレースせずに誤所からプレーしたので、一般の罰を受けます。(規則9.4、14.7)
競技終了前に発覚した事実だったので、委員会はそのホールのスコアに含めるべきであった罰打を加え、
2ndラウンドの13番ホールのスコアを「6」から「8」に修正しました。(規則3.3b(3))
この件に関して非常に残念なポイントが3つあります。
1つは笠選手自身が要請前に行った処置の誤りに気付き、立ち会った競技委員に伝えてほしかったことです。
2つ目は立ち会った競技委員も選手が行った処置を一から具体的に聞いてほしかったことです。
3つ目はJLPGAから発表された「視聴者による指摘で発覚したルール違反」という内容です。
2021年以降、JLPGAは一般視聴者によるルール違反の指摘は受け付けない方針にしていますが、
大会関係者がモニターを見て気づいた違反を「視聴者」という誤解を招く言葉で表現したことで訂正が入り、
問題を更に大きくしてしまいました。
また、この件で「選手は失格ではないか」という質問を多く受けましたが、これは大きな誤りです。
選手は委員会から指摘されるまで自身の誤りに気づいておらず、
今回のように競技終了前に発覚した場合は
そのホールのスコアに含めるべきであった罰打を加えることでホールのスコアを修正します。
もし、競技終了後に発覚した場合は、
競技が終了する前に選手は罰を受けていたことを知らなかったため、
「6」で提出したスコアは訂正してはなりません。(規則20.2e(2))
つまり、13番ホールのスコアは6のままで罰打を加えることなく、また失格にもなりません。
アマチュアの模範であるプロゴルファーはゴルフ規則を知っておくべきですが、プロも人間ですので勘違いや失敗もあります。
当然のことながら心無いコメントに傷付きます。
どうか温かい目でプレーヤーを見守って頂けますと幸いです。
- 5月10日(土)
- くい込んだ球の判断と処置解説:(JLPGA競技委員)阿蘇紀子さん、中崎典子さん
JLPGAツアー開幕のダイキンオーキッドレディスは沖縄の琉球ゴルフ倶楽部で開催されましたが、
そこで起きたルーリングをもとに「くい込んだ球の判断と処置」を解説します。
琉球ゴルフ倶楽部の芝はコーライでラフはティフトンが混じっていることにより、
ラフに打ち込んでしまうと球全体が沈んでしまい、とても難しいショットになります。
そして球全体がラフに沈むと、プレーヤーは地面にくい込んでいるのではないかと確認のためルーリングを呼ぶことが多々あります。
実際、トーナメント初日の1番ホール左ラフでくい込んだ球かの確認でルーリングに呼ばれました。
状況を調べてみると、その球は地表面よりも下にはなかったため、救済は認められませんでした。
このルーリングが今年JLPGAツアー最初のルーリングで、立ち会った私はファーストペンギンになりました。
ファーストペンギンとは
ペンギンの群れの中から天敵がいるかもしれない海に魚を求めて最初に飛び込む勇敢なペンギンなのですが、
それに比喩して委員会はこれから始まる長いシーズンの最初にルーリングに立ち会った競技委員にその名称を与えます。
委員会の慣例でファーストペンギンはご飯をご馳走してもらえます。
それはさておき、そもそも
地面にくい込んでいる球で罰なしの救済が認められるのはジェネラルエリアにある球、
例えばラフやフェアウェイ、カラーにある場合のみです。
そして、プレーヤーの直前のストロークの結果作られた自らのピッチマークの中にあり、
その球の一部が地表面以下にある場合です。(規則16.3a(1)(2))
稀に、フェアウェイに転がった球が別のプレーヤーの作ったピッチマークに入ってしまうことがあります。
そのような場合は罰なしの救済はありません。
そのため、後からプレーするプレーヤーへの配慮とコースの保護を目的として
フェアウェイなどでも自ら作ったピッチマークはストロークした後に修復することをお勧めします。
プレーヤーは球が地表面を割っているのか確認するのに、
球をマークして拾い上げることができます。(規則16.4)
このときに拾い上げた球を拭くことはできませんので注意が必要です。(規則16.4)
球を拾い上げた後、ピッチマークが地表面以下にあるのか目視で判断できない場合、
ライを改善しないように気を付けながら、手で地面に触れて確認することがあります。
この時点で救済が認められないと判断すれば、その球を元の箇所にリプレースします。
救済が認められる場合は、球が地面にくい込んでいる直後の箇所を基点として、
ホールに近づかない、1クラブレングスのジェネラルエリアに球をドロップすることによって
救済を受けることができます。
このときに球を拭いたり取り替えたりすることもできます。(規則14.3a、14.1c)
2023年から新たに追加された詳説に球の直後の箇所がジェネラルエリアではない場合の救済があります。(詳説16.3b/1)
このような状況は、球がジェネラルエリアにくい込んでおり、
球の直後の箇所がバンカー、ペナルティーエリア、またはアウトオブバウンズの場合があります。
このような状況ではホールに近づかないジェネラルエリアの箇所を見つけるために
左右や後ろに幾らかの距離を取ることが必要となるかもしれません。
くい込んだ球の処置を覚えていただけるとご自身のプレーに役立つことがあるかもしれません。
- 5月17日(土)
- ダウンスイングでアイアンのシャフトが折れる解説:(JLPGA競技委員)阿蘇紀子さん、中崎典子さん
米ツアー、3月に開催されたブルーベイLPGAは竹田麗央選手の優勝で嬉しいニュースが日本まで届きました。
大会初日の4番ホール、パー3で馬場咲希選手に珍しいハプニングが起こりました。
彼女はティーショットのためのダウンスイングに入ったところ、
なんと5番アイアンのシャフトが真っ二つに折れてしまいました。
折れたクラブによって球は動かされることなく、馬場選手はスイングを止めて唖然としていました。
要請された競技委員から1打目はストロークとしてカウントしないと裁定され、
1番手大きなクラブに持ち替えて打ち直したそうです。
定義のストロークとは「球を打つために行われるクラブの前方への動き」です。
つまり、ダウンスイングに入った時点でストロークは開始され、
その時点でクラブヘッドがシャフトから外れようが、
シャフトが真っ二つに折れようが、球を打ったかどうかに関わらず、
スイングを続けた場合はストロークとしてカウントされます。
しかし、馬場選手の裁定はノーカウントだったので、ダウンスイングの間に球を打たないことを決めて、
そのクラブヘッドを意図的に止めようとして打つことを避けたと考えられます。
この場合はストロークとしてカウントされません。(定義:ストローク)
オフィシャルガイドの詳説には、ストロークとしてカウントされない例として、
「ダウンスイングの途中でプレーヤーのクラブヘッドがシャフトから外れた。
そのプレーヤーは球に届く前にダウンスイングを止めたが、
そのクラブヘッドが落下し、その球に当たって動かした。」とあります。(詳説:ストローク/1)
興味深いことに、もし、このようなことがホールのプレー中に起きた場合、
ストロークとしてカウントされないものの、
規則9.4に基づき、インプレーの球を動かしたことによる1罰打は免れません。
そして、その動かされた球を元の位置にリプレースしなければなりません。
しかし、馬場選手はホールをスタートするためのティーイングエリアでの出来事でしたので、
例えクラブから外れたヘッドが球に当たったとしても罰はありません。
これは、ルールザワールドの振り返りで3月15日のティーイングエリアにてご参照ください。
- 5月24日(土)
- 「教えて!Nory」解説:(JLPGA競技委員)阿蘇紀子さん、中崎典子さん
【質問】
質問です。
アマチュアでもプロの試合でもよく見かけますが、パターでパッティンググリーンをトントンしていますよね。
あれはずっとモヤっとしていました。
そこでノーリー様の早わかり集を購入して読んでみると130ページに
プレーヤー自身がつけたボールマーク、スパイクマーク、人が引っ掻いた傷や動物の足跡など記載してありましたが、
ラインを読んだ後、念入りにトントンする人がいます。
それはどの程度良いのでしょうか?
モラルの問題なのか、時間をかけスロープレーになる人もいます。
ぜひ教えてください。
【解説】
ご質問者様、ご質問ありがとうございます。
解答から申しますと、
プレーヤーがパッティンググリーンを元の状態に復元するために合理的な範囲を超える行動、
例えば、ホールへの道を作ることによってパッティンググリーンを改善した場合、
そのプレーヤーは規則8.1aの違反に対して2罰打(一般の罰)を受けます。(規則13.1c(2))
そもそもパッティンググリーン上の損傷の修理は不当にプレーを遅らせることなく行わなくてはなりません。
不当にプレーを遅らせた場合の最初の違反は1罰打、2回目の違反は2罰打(一般の罰)、
そして3回目の違反は失格になります。(規則5.6a)
この質問はある試合でプロからも受けたことがあります。
彼女は「合理的な範囲を超える行動」とはどのように判断すれば良いのかとあまり納得していませんでしたが、
残念ながらオフィシャルガイドにはそれ以上のことは書かれていません。
もし現場で私が裁定を求められたら、
あまりに度を超えてパターでパッティンググリーンをトントンしているのであれば1回目はその選手を注意します。
必要であれば、ラウンドが終了した後にパッティンググリーン上で修理して良いものとしてはならないものを指導し、
プレーが不当に遅れないように注意します。
それでも後日、彼女の行動が改善しない場合は、
現場にいるレフェリーの判断に基づいて
プレーヤーに規則8.1aの違反による2罰打か規則5.6aの違反による1罰打を課すことでしょう。
- 5月31日(土)
- 外的影響によって木の上になった球が動かされた解説:(JLPGA競技委員)阿蘇紀子さん、中崎典子さん
JLPGAツアー開幕のダイキンオーキッドレディスは沖縄の琉球ゴルフ倶楽部で開催されましたが、
大会3ラウンド目の3番ホールのパー3で起きたルーリングをもとに木の上になった球が動かされた場合の救済と処置を解説します。
あるプレーヤーの193ヤードのティーショットはかなり左に飛んでしまい、
胸ぐらいの高さの小さな木の枝の上に球が止まりました。
試合観戦に来ていたギャラリーの小学生低学年ほどの女の子はプレーヤーの球だと思わず、
手を伸ばしてその球を掴んでしまいました。
周りのギャラリーに注意されたその女の子は動揺して泣いてしまいましたが、
球があった元の箇所を示してくれました。
この場合、女の子は規則上、外的影響になります。
外的影響とはプレーヤーの球、用具、コースに起きることに影響を及ぼす可能性のあるプレーヤーや
そのキャディーを除くすべての人、動物、自然物などを指します。(定義:外的影響)
プレーヤーの球が外的影響によって動かされた場合、
プレーヤーは罰なしにその球を元の箇所にリプレースしなければなりません。(規則9.6)
その箇所がわからない場合は推定位置に戻します。
外的影響が動かした事例は他にもカラスが球を咥えていった、
レポーターが誤ってコースにあるプレーヤーの球を蹴飛ばしたなどがあります。
これもすべて外的影響が球を動かしたことになります。
このケースでは、罰なしに木の上に球をリプレースした後にその箇所からあるがままにプレーすることができます。
しかし、プレーヤーはその球をリプレースの処置を省略して、1罰打でアンプレヤブルの球とみなしました。
アンプレヤブルの球の処置は3つの選択肢があります。
ストロークと距離の救済、後方線上の救済、そしてラテラル救済です。(規則19.2)
プレーヤーはラテラル救済を選択し、球が木の上にあった箇所の真下の地面の地点を基点として、
そこからホールに近づかない2クラブレングス以内の救済エリアに球をドロップすることで処置を終了しました。(規則19.2b)
ホールアウト後、プレーヤーは泣きじゃくる女の子にサイン入りのボールをあげて次のホールへ歩いて行ったそうです。
仮にプレーヤーがストロークを行う前に球が外的影響によって動かされていたことを知らずに
球の止まった箇所からストロークを行った場合、罰はありません。(規則9.2a)
それは、プレーヤーにとって球が動かされたことはストローク前には知らなかった事実であり、
「分かっている、または事実上確実」ではなかったからです。(規則9.2b、定義:分かっている、または事実上確実)